こんにちは、いちもくです。
「昔はもっと本が読めたのに」
「最近、読書が楽しめなくなった」
そんな感覚を抱えている人は多いはずです。
でも、それはあなたの怠慢でも、意志の弱さでもありません。
本書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、忙しい現代人が直面する「読書ができない理由」を、労働と文化の歴史から丁寧にひもとく一冊です。
仕事に追われ、余白のない生活を送る現代人が、なぜ本を手に取れなくなったのか?
そして、それでもどうすれば読書の時間を取り戻せるのか?
読み終えたとき、「本を読みたい」という気持ちが、静かに、しかし力強くよみがえります。
本書の要点
1. 現代日本では、文化に時間を割けない働き方が標準化されています。
2. インターネットで得られる「情報」と読書で得られる「知識」の違いを理解する必要があります。
3. 読書を生活の一部にするためには、様々な分野に「半身」で取り組むアプローチが重要です。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の必読ポイント
仕事優先社会の形成

明治時代以降、日本の労働観は大きく変遷してきました。
本書では、各時代を代表するベストセラーや社会現象を手がかりに、日本人がどのように「働く」ことと向き合ってきたのかを丁寧に紐解いていきます。
明治時代の自己啓発書の隆盛に見られる勤勉性の称揚、高度経済成長期におけるモーレツ社員の台頭、そして現代の「仕事がアイデンティティ」となる社会まで。
時代とともに変化する労働観の背景には、常に「効率性」の追求がありました。
効率化の名の下に、労働時間は長時間化し、私たちの生活は仕事中心に塗り替えられていきました。
ゆっくりと読書に耽る時間、趣味に没頭する時間は「無駄」と見なされ、削られていく。
結果として、現代社会では「本を読まない」ことが当たり前になってしまったのです。
仕事以外の活動を「人生のノイズ」と捉え、排除しようとする現代人の姿は、どこか息苦しさを感じさせます。
その結果、読書などの文化的活動に充てる時間が著しく減少している実態が明らかにされています。
ノイズこそが、読書の醍醐味

SNSやニュースサイトでは、必要な情報が瞬時に手に入ります。
しかし、本書が指摘するのは「情報」と「知識」はまったくの別物であるという点です。
読書とは、目的を持って情報を取る行為ではありません。
むしろ、想定外の内容や思いがけない発見に出会う「ノイズ」に価値があります。
思わぬ発見、新しい視点との出会いは、人生を豊かに彩るスパイスとなるでしょう。
しかし、現代の労働環境では、この「ノイズ」を歓迎する余裕がありません。
成果が求められ、スピード重視で効率よく働く現代人にとって、読書のような「役に立つかどうかわからないこと」に時間を使うのは贅沢とされがちです。
この「ノイズ=無駄」という価値観が、読書の楽しさを奪っているのだと、著者は警鐘を鳴らしています。
「全身全霊」ではなく「半身」で働くという選択肢
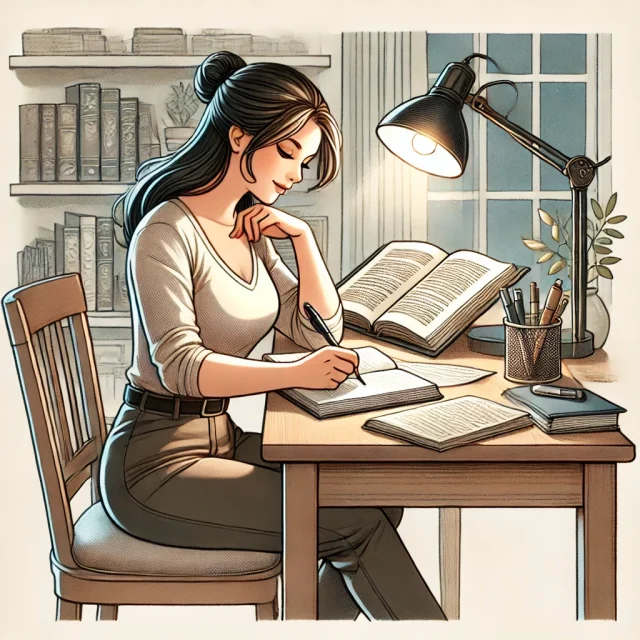
では、どうすれば私たちは再び本を読めるようになるのでしょうか。
著者が提案するのは、「全身全霊で働く」ことをやめ、「半身」で複数の世界に関わる生き方です。
これは中途半端に生きろ、という意味ではありません。
むしろ、ひとつの役割に自分を全振りせず、仕事と趣味、労働と教養、利益と好奇心のあいだを、行き来できる自分をつくることが大切だというのです。
例えば、定時で帰る努力をすること。
週末にスマホをあえて見ない時間をつくること。
読みたい本を机の上に置いておくこと。
そんな小さな工夫が「半身」の第一歩になります。
著者自身も、会社員として働きながら執筆活動を続けてきました。
忙しくても「半分の自分」で本と関わる時間を持ち続けてきた経験が、本書の説得力を支えています。
さいごに
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、読書という行為がなぜこんなにも難しくなってしまったのか、その背景と原因を歴史と社会の文脈から解き明かしています。
同時に、それでも本を読むためにはどうすればいいのか――という問いに、実践的なヒントと希望を与えてくれる一冊です。
読書は「ノイズ」であり、「寄り道」です。
ですが、その寄り道こそが、人生を少しだけ豊かにしてくれるのです。
読み終わる頃には、あなたもきっと、読みかけの本をもう一度手に取りたくなっているはずです。
そして、こう思うでしょう。
「読書のために生きることも、悪くないな」と。
それじゃ、またね。
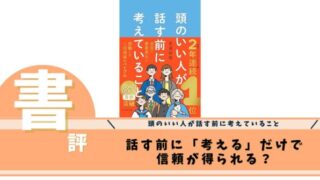
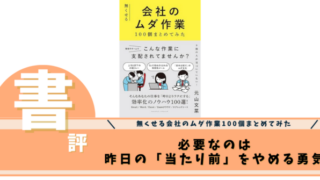
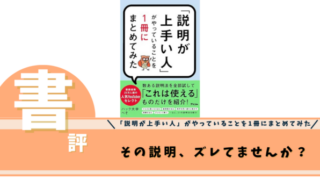



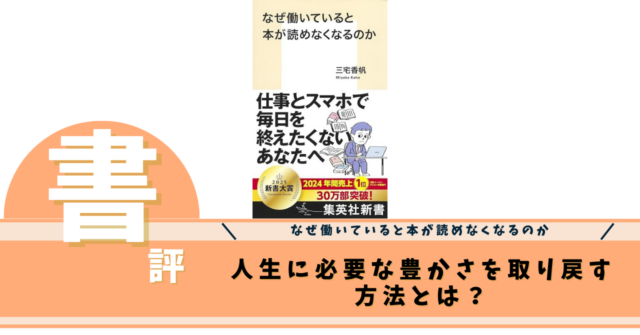

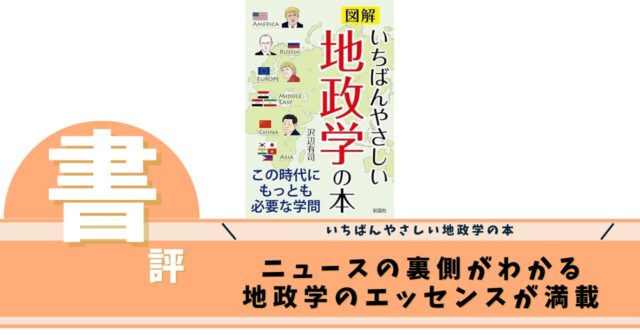
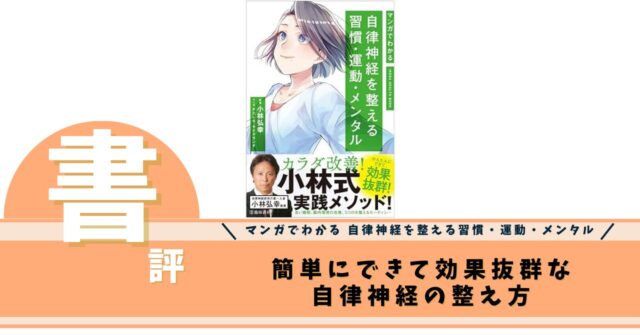

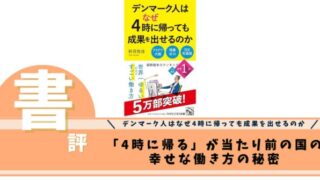
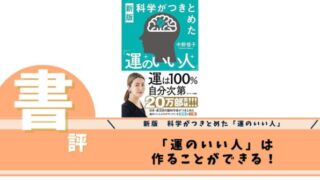

コメントを投稿するにはログインしてください。