こんにちは、いちもくです。
お子さんが生まれたら、多くの親御さんが考えるのが「教育資金をどうやって準備しよう?」ということ。
大学進学費用だけでも数百万円が必要な時代、早めの準備が欠かせません。
教育資金の準備方法として人気なのが「学資保険」と「貯金」です。
でも、実際のところどちらが良いのでしょうか?
この記事では、学資保険と貯金のメリット・デメリットを詳しく比較し、あなたのご家庭にぴったりの選択肢をご提案します。
学資保険と貯金はどちらがおすすめ?

学資保険は「計画的に積み立てたい人」や「保険機能も一緒に欲しい人」に向いています。
一方で、貯金は「自由度を重視する人」や「自分で資産管理ができる人」に向いています。
どちらが優れているというより、家庭の考え方やリスク許容度によって選ぶべき手段が変わってきます。
学資保険とは

学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するための生命保険です。
毎月決まった保険料を支払い、子どもが一定の年齢(15歳、18歳など)に達したときに、まとまったお金を受け取れる仕組みになっています。
多くの学資保険では、契約者(多くは親)に万が一のことがあった場合、以後の保険料支払いが免除され、予定していた教育資金は確実に受け取れる保障がついています。
また、商品によっては子どもの医療保障がセットになっているものもあり、教育資金の準備と保障を同時に備えることができます。
学資保険を活用するメリット
強制的に貯金できる仕組み
学資保険は毎月自動的に口座から保険料が引き落とされるため、意志が弱くて貯金が続かない人でも確実に教育資金を準備できます。
「今月は余裕がないから貯金をやめよう」という誘惑に負けることがありません。
契約者に万が一のことがあっても安心
もし契約者(親)が死亡や高度障害状態になった場合、以後の保険料支払いが免除され、満期時には予定通りの教育資金を受け取れます。
これは貯金にはない大きな安心感です。
元本割れリスクが比較的低い
現在の低金利時代でも、多くの学資保険で返戻率(払い込んだ保険料に対する受取総額の割合)が100%を超える商品があります。
安全性を重視しながら、わずかながらでも増やすことができます。
税制上の優遇措置がある
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税の軽減効果があります。
年間の控除額には上限がありますが、税金面でのメリットも期待できます。
計画的な受取時期を設定できる
中学・高校・大学入学時など、お金が必要になるタイミングに合わせて受取時期を設定できます。
子どもの成長に合わせた資金計画が立てやすくなります。
学資保険を活用するデメリット
途中解約すると元本割れのリスク
契約から短期間で解約した場合、払い込んだ保険料よりも解約返戻金が少なくなる可能性があります。
長期継続を前提とした商品のため、途中でやめてしまうと損をしてしまいます。
インフレに対応できない
学資保険は契約時に受取額が確定するため、将来的に物価が上昇(インフレ)した場合、実質的な価値が目減りしてしまう可能性があります。
20年後の100万円と今の100万円では価値が異なるかもしれません。
他の投資商品と比べると利回りが低い
安全性を重視している分、株式投資や投資信託などと比べると期待できるリターンは低くなります。
より高い運用益を求める方には物足りないかもしれません。
保険会社の破綻リスク
万が一、保険会社が経営破綻した場合、契約内容が変更されたり、受取額が減少したりする可能性があります。
生命保険契約者保護機構による保護はありますが、100%の保障ではありません。
資金の流動性が低い
急にまとまったお金が必要になっても、学資保険は簡単に現金化できません。
貯金のように自由にお金を引き出すことができないため、家計の急変に対応しにくい面があります。
貯金とは

貯金とは、銀行などの金融機関に現金を預けて蓄えることです。
普通預金、定期預金、積立定期預金など、様々な種類があります。
教育資金準備の文脈では、毎月一定額を積み立てて将来の教育費に備える方法を指すことが多く、自動積立定期預金などを活用する家庭が多いです。
元本保証があり、預金保険制度によって1金融機関あたり元本1,000万円とその利息まで保護されるため、安全性の高い資金準備方法として多くの人に選ばれています。
貯金を活用するメリット
自由度が高い
貯金は必要に応じていつでも引き出すことができます。
急な医療費や家計の変化、予想外の教育費が必要になったときでも、柔軟に対応できる自由度の高さが最大の魅力です。
元本保証で安心
銀行預金は元本が保証されているため、払い込んだお金が減ることはありません。
預金保険制度により、万が一銀行が破綻しても一定額まで保護されるため、安全性は非常に高いです。
手数料がかからない
学資保険のような手数料や諸費用がかからないため、貯めたお金がそのまま教育資金として活用できます。
シンプルで分かりやすい仕組みです。
金利上昇の恩恵を受けられる可能性
将来的に金利が上昇した場合、その恩恵を受けることができます。
特に変動金利の商品であれば、金利環境の改善によって利息収入の増加が期待できます。
目標金額の調整が簡単
子どもの進路変更や家計状況の変化に応じて、貯金額を増やしたり減らしたりといった調整が簡単にできます。
フレキシブルな資金計画が可能です。
貯金を活用するデメリット
低金利で増えにくい
現在の日本は超低金利時代で、普通預金の金利は年0.001%程度です。
定期預金でも年0.01%程度と非常に低く、インフレを考慮すると実質的に目減りしている可能性があります。
貯金の意志が続かないリスク
自由に引き出せる分、「今月は家計が苦しいから」「欲しいものがあるから」といった理由で貯金を中断してしまうリスクがあります。
強い意志と継続力が必要です。
万が一の保障がない
貯金している親に万が一のことがあっても、それまでに貯めた分しか教育資金がありません。
学資保険のような保障機能はないため、リスクは自分で備える必要があります。
税制優遇がない
預金の利息には20.315%の税金がかかり、学資保険のような所得控除もありません。
税制面でのメリットは期待できません。
インフレリスクに弱い
物価上昇に対して貯金の価値は相対的に下がってしまいます。
20年後に必要な教育費が想定以上に高くなっていた場合、準備した貯金では不足する可能性があります。
結局、学資保険と貯金はどちらがおすすめ?
ここまでそれぞれのメリット・デメリットを見てきましたが、結局どちらを選ぶべきでしょうか?
貯金習慣に自信がなく、確実に教育資金を準備したい方は学資保険がおすすめです。
強制的に貯められる仕組みと万が一の保障は、大きな安心感をもたらします。
一方で、自分でしっかりと貯金でき、資金の自由度を重視したい方は貯金がおすすめです。
急な出費への対応力と、金利上昇時の恩恵を受けられる可能性は魅力的です。
実は、多くの家庭では「学資保険と貯金の併用」が現実的な選択肢になっています。
基本部分は学資保険で確実に準備し、追加分や緊急時の備えとして貯金も並行して行う方法です。
重要なのは、まず行動を起こすこと。
完璧な選択を求めて準備が遅れるよりも、どちらかの方法で今すぐ教育資金の準備を始めましょう。
さいごに
教育資金の準備は、早く始めるほど月々の負担が軽くなり、より確実に目標を達成できます。
お子さんの将来の選択肢を広げるためにも、今日から準備を始めませんか?
学資保険も貯金も、それぞれに良さがあります。
大切なのは、あなたのご家庭の価値観や状況に合った方法を選ぶことです。
もし学資保険に興味を持たれた場合は、複数の保険会社の商品を比較検討し、返戻率や保障内容をしっかりと確認してから契約することをおすすめします。
きっと、お子さんの明るい未来への第一歩になることでしょう。
将来のお子さんの笑顔を思い浮かべながら、今できることから始めてみてください。
あなたの愛情のこもった準備が、きっとお子さんの夢を支える力になりますよ。
それじゃ、またね。


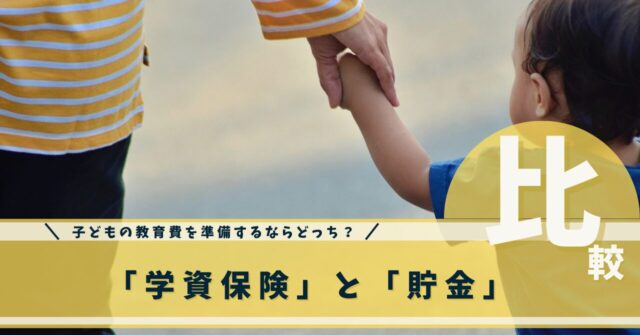



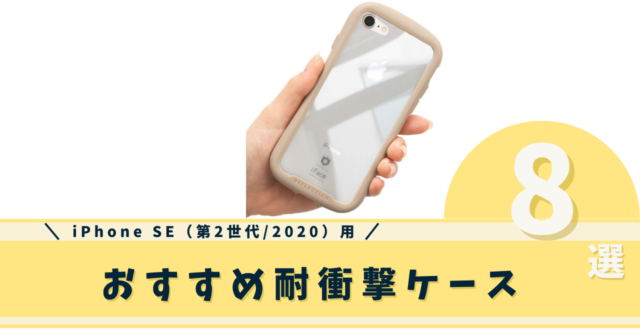




コメントを投稿するにはログインしてください。