こんにちは、いちもくです。
「頑張って説明したのに、伝わらなかった」
「説明したつもりが、相手の反応が微妙」
そんな経験、誰にでもあるはずです。
理路整然と話したのに響かない。
結論から話したのに伝わらない。
ビジネス書や自己啓発本で見かける“正しい説明法”を実践しても、なぜかうまくいかない。
そんな「説明迷子」にこそ読んでほしいのが、『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』です。
著者は人気YouTuber「ハック大学 ぺそ」氏。
本書では、世間でよく言われる“説明のコツ”がなぜ機能しないのか、そして本当に伝わる説明とは何かを、豊富な例とともに解説しています。
本書の要点
- 説明する前に「相手」と「目的」を確認しよう。
- 数字を使って説明しよう。なければ「仮説思考」で補う。
- 「抽象から具体へ」の順で話すと、伝わりやすい。
「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみたの必読ポイント
説明は「内容」より「相手」ファースト

多くの人は「何を話すか」に意識を向けがちですが、伝わる説明は「誰に話すか」がスタート地点。
本書では、相手の知識レベル・立場・関心に合わせて説明方法を変える重要性が語られています。
たとえば「サブスクって何?」と聞かれたとき、相手がIT業界の人なら業界用語を交えても問題ありません。
しかし、全く知らない人なら「月額の焼き肉食べ放題みたいなもの」といった具体例を使うべきです。
説明の目的が「理解」なのか、「共感」なのか、「行動」なのかによっても、選ぶ言葉や構成は変わってきます。
つまり、説明力は“会話力”でもあるのです。
数字は「共通の物差し」になる

ビジネスの現場では、「数字を入れた説明ができるか」が説明力の分かれ目。
数字は誰にとっても共通の基準であり、主観的な話を客観的に見せてくれる道具です。
たとえば「今月の売上はけっこう良かったです」ではふわっとしすぎ。
でも「先月比120%の売上です」と言えば、相手は瞬時に状況をイメージできます。
それでも、使える数字が手元にない場合もあります。
そんなときは「仮説思考」で乗り切るのが本書の教え。
例えば「仮にこの施策でコンバージョン率が3%上がれば、月間で新規顧客が○○人増える見込みです」といった仮定を置くことで、説明に説得力が増します。
話が長い人は「抽象→具体」の順で整理する

「話がわかりにくい」と言われる人の多くは、話の順番がバラバラ。
いきなり細かい話から入ってしまい、全体像がつかみにくくなるのです。
本書では「抽象から具体へ」というシンプルなフレームが紹介されています。
まず大枠の考えやポイントを提示し、その後に具体例やエピソードを足す。
そうすることで、聞き手は「いま何の話をされているのか」が迷子にならず、理解がスムーズになります。
たとえば新しいプロジェクトの説明なら、
「この施策の狙いはAです。そのためにBとCの2つのアプローチを考えています。具体的には…」
といった流れが理想です。
さいごに
説明が下手だと、損します。
相手に誤解され、信用されず、チャンスを逃します。
でも、それは才能ではなく「技術」の問題。
ちょっとした工夫や視点の切り替えで、説明力はぐっと変わるのです。
『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』は、そんな“説明迷子”を脱するための、実践的なヒントが詰まった一冊。
読み終えたときには、「あの説明の何が悪かったのか」「これからどう説明すればいいか」が見えてきます。
「伝わらない」の壁にぶつかっているすべての人に、強くおすすめしたい本ですよ。
それじゃ、またね。
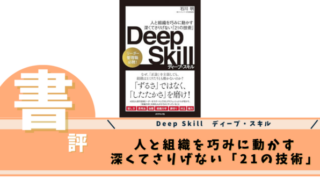
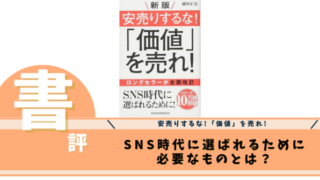
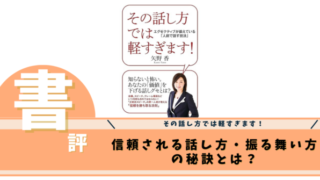



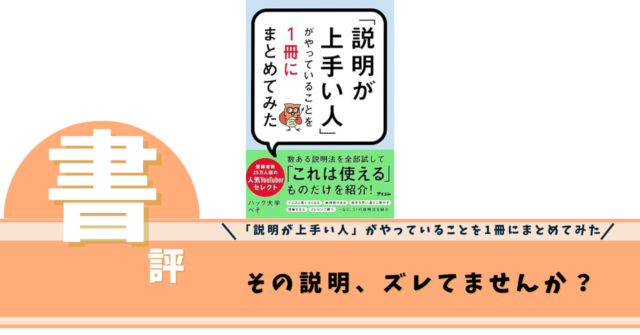


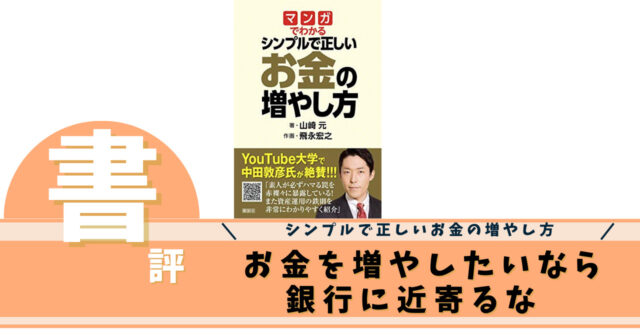
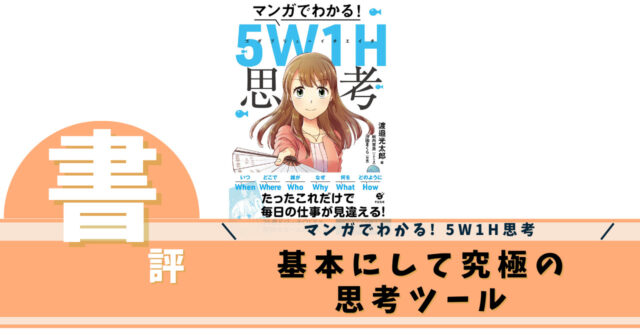

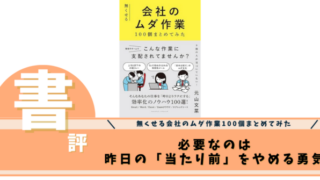

コメントを投稿するにはログインしてください。