こんにちは、いちもくです。
お茶にはたくさんの種類がありますが、真っ先に思い浮かべるのはやはり日本茶ではないでしょうか。
でも、そもそも「日本茶」とは具体的に何を指しているのでしょう?
一般的には「日本で生産された緑茶」のことを、日本茶と呼んでいる場合がほとんどです。
日本で生産されるお茶は、ほとんどが緑茶。
お茶にはたくさんの種類がありますが、 元々は同じ茶葉からできています。
育て方や仕上げ加工の違いによって、 様々な味や香りのお茶となっているんです。
それぞれお茶の趣を理解できれば、飲みたいシーンや料理に合わせて飲み分けることもできます。
今回は、日本茶の種類と歴史について詳しく解説していきます。
日本茶の歴史
お茶の伝来
お茶が日本に伝わったのは、奈良時代頃だと考えられています。
『日本後記』には、西暦815年に嵯峨天皇へ僧の永忠が茶を煎じて献上したという記録が残っています。
永忠は、805年までの約35年間、遣唐使として唐で仏教を学んでから日本に帰国しました。
永忠が帰国時に持ち帰ったお茶は、団茶と呼ばれるものだったと伝えられています。
団茶とは、蒸したお茶の葉を円形に押し固め、乾燥させたもの。
当時はそれを削って、お湯に煎じて飲んでいたと言われています。
抹茶の普及
永忠が嵯峨天皇にお茶を献上してから約400年後の1191年、禅僧の栄西が宋からお茶を持ち帰ります。
栄西は、お茶だけでなく、抹茶の作法も日本に持ち帰ったとされています。
栄西は日本に戻ると、『喫茶養生記』という本を書き、抹茶を日本に広めます。
この本には、お酒を飲んだ後に抹茶を飲めば、悪酔いを防ぐことができるといったいったように、お茶の効能が詳しく書かれています。
栄西は、宋から持ち帰ったお茶の木を各地に植えました。
当時、京都の宇治にもたくさんのお茶の木が植えられたと伝えらえています。
現在も、宇治はお茶の名産地。
宇治のお茶栽培は、1000年近い歴史があることになります。
茶道の完成
日本で茶道が完成するのが、16世紀。
茶道を完成させたのは千利休です。
利休は、禅の精神である侘びの世界を、お茶の作法と融合させました。
利休が茶道を完成させた頃、中国では抹茶が廃れて、煎茶が飲まれるようになっていました。
この煎茶を日本に紹介したのは、僧の隠元。
1654年に、明から日本に渡ってきた僧です。
隠元によって、現在まで続く煎茶の歴史が日本で始まります。
この頃から、貴族や上流階級がたしなむ抹茶に代わり、一般庶民が煎茶を飲むようになりました。
本当に美味しいものとは
織田信長は、「湯漬け」を好んで食べていました。
湯漬けは御飯にお湯をかけて食べる料理です。
これが「お茶漬け」になると、風味や味が増すので、格段に美味しくなります。
中国の『菜根譚』には
本当に美味しいものとは、淡白な味のものである。
ゴテゴテした脂っこい食べ物は、本当の美味しいものとは言えない。
と書かれています。
湯漬けだと淡白すぎるかもしれませんが、うっすらとしたお茶の風味が加わったお茶漬けは、菜根譚に書かれている本当に美味しいものと言えそうです。
日本茶の種類
現在市販されている日本茶は、茶の湯で使う抹茶をはじめ、玉露、番茶など、さまざまな種類があります。
煎茶
煎茶とは、生葉を蒸して細長くねじったもの。
4月下旬から5月中旬に摘んだものを一番茶、6月下旬に摘んだものを2番茶、8月に摘んだものを3番茶と呼びます。
深蒸し煎茶

煎茶よりも豊富な蒸気を用いて、蒸す時間を煎茶よりも2~3倍長くしたものが深蒸し茶。
煎茶よりも渋味が抑えられた味わいを楽しめます。
玉露

新芽が出てすぐ、覆いをして直射日光に当てないように育てた茶葉を使ったお茶。
煎茶よりも鮮やかな緑色をしています。
旨味が凝縮された、高級茶です。
玉露の新茶が出回るのは、10月頃になります。
番茶
直射日光を十分受けて育っており、殺菌効果に優れています。
蒸し製玉緑茶
煎茶よりも濃厚な味わいが魅力です。
芽茶
1本の茎に1つしかない、茶葉の先端部分だけを集めた高級茶です。
焙じ茶

番茶や煎茶の古くなったものを強火で焙じて、香ばしい香りをつけたお茶。
自宅にある古くなった茶葉を焙じても、簡単につくれます。
自分で焙じれば、市販の焙じ茶よりも更に香ばしさ堪能できます。
玄米茶
茶葉の質よりも、玄米の量や質によって味が左右されます。
粉茶

お茶の製造工程の仕上げ段階で出る、粉だけを集めてつくったお茶です。
抹茶

日よけを使って育てたてん茶を、茶臼で挽いて粉末にしたお茶です。
さいごに
昔から日本では、食前と食後にお茶を飲む習慣があります。
淡白で、かつ渋みもある味が、醤油や味噌を使った和食にぴったり合います。
日本で生産されるお茶は、ほとんどが緑茶。
お茶にはたくさんの種類がありますが、 元々は同じ茶葉からできています。
育て方や仕上げ加工の違いによって、 様々な味や香りのお茶となっているんです。
それぞれお茶の趣を理解できれば、飲みたいシーンや料理に合わせて飲み分けることもできますよ。
それじゃ、またね。
参考文献
日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ (新潮文庫)
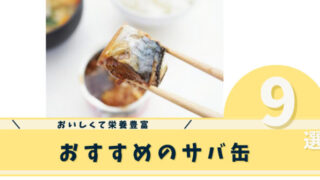


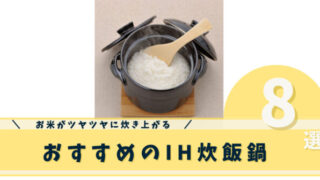


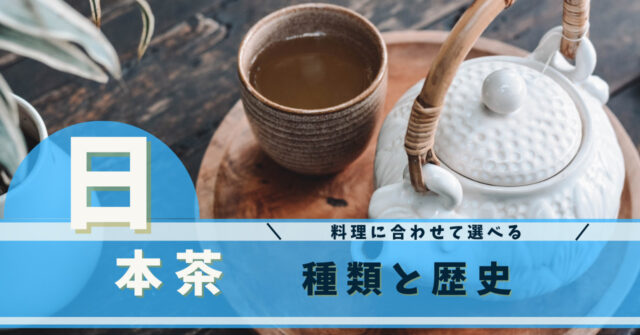
















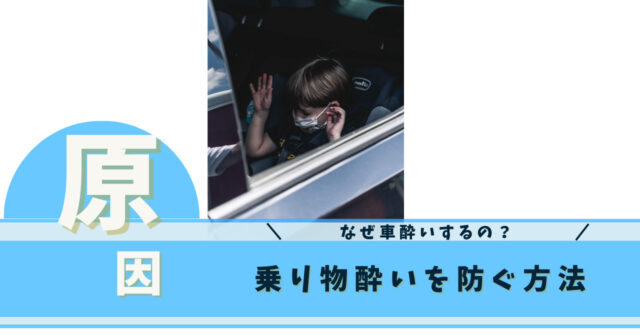
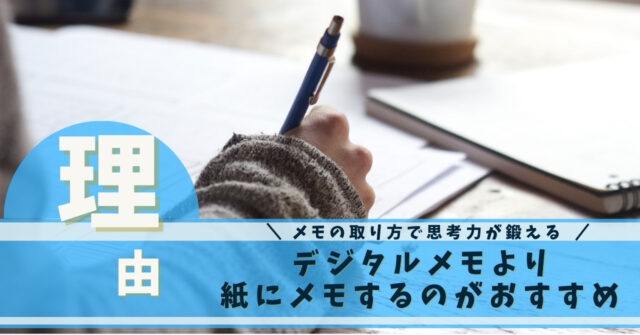

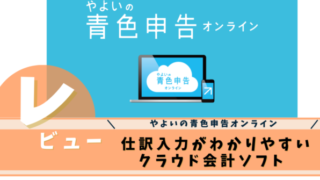


コメントを投稿するにはログインしてください。