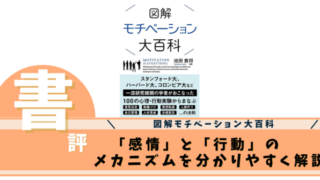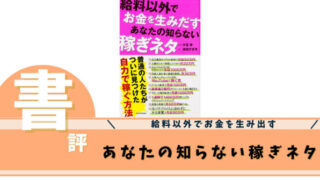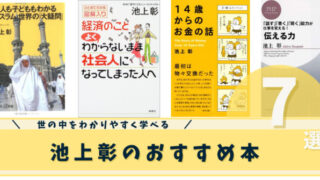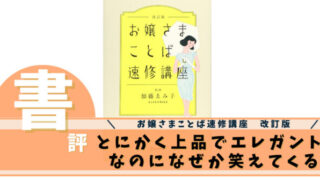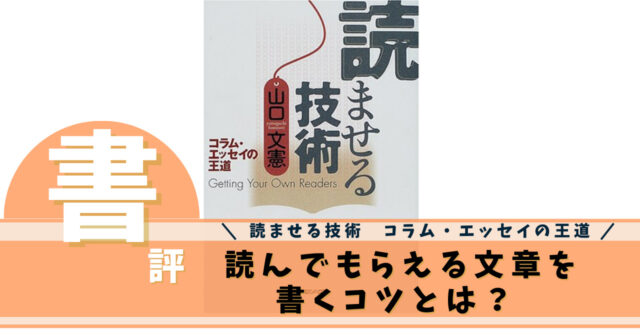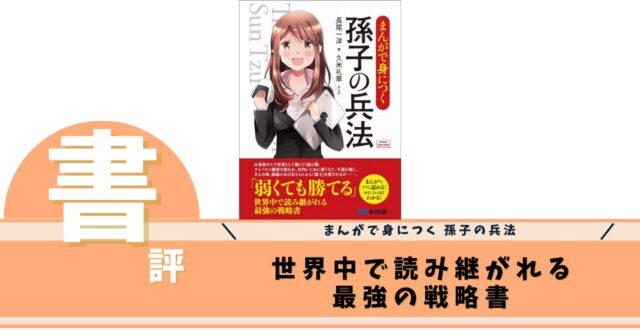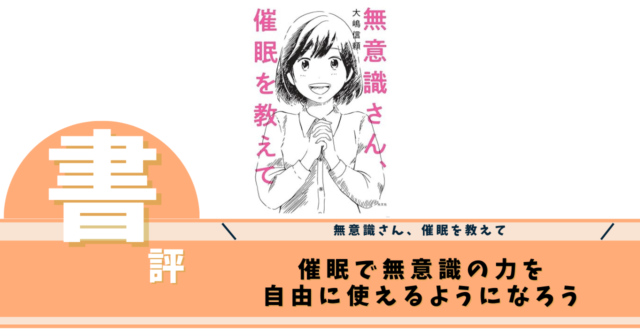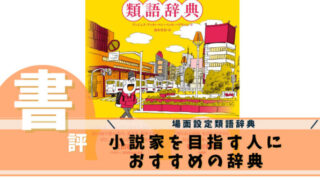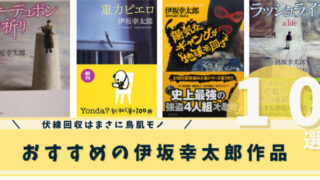こんにちは、いちもくです。
いざ文章を書こうと思っても、なかなかいいフレーズが思い浮かばずに筆が進まないことはありませんか?
そんな人におすすめなのが、うまい文章を書こうとしないこと。
うまい文章を書く秘訣はありませんが、まずい文章を書かないコツはあるんです。
そんな文章のコツを、ちょっぴり厳しめに教えてくれるのが「読ませる技術 コラム・エッセイの王道」。
エッセイストの山口文憲さんが講義した、コラム・エッセイに関する講座内容をまとめた本です。
そもそも、うまく書けそうもないことは書かなければいいんです。
自分が書きたいことではなく、人が読みたいことを書く。
読ませる文章とはいったいどのようなものなのか、本書を読めばその答えが見えてくるはずです。
読ませる技術 コラム・エッセイの王道
| 初版発行 | 2001年3月22日 |
| 著者 | 山口文憲 |
| 発行所 | 株式会社マガジンハウス |

『読ませる技術 コラム・エッセイの王道』の魅力
自分が書きたいことを書いても、人は読んでくれない
『読ませる技術 コラム・エッセイの王道』は、著者の山口文憲氏が実践してきた、コラム・エッセイ講座の経験をもとにして書かれています。
本の冒頭に、
うまい文章を書く秘訣はないが、まずい文章を書かないコツはある
という一文が書かれています。
本書の内容は、まさにこの一文に凝縮されているといっても過言ではありません。
自分が書きたいことを書いても、人は読んでくれません。
人が読みたいことを書くのが、読んでもらえる文章のコツなんです。
【必読ポイント】いい文章を書くための6つのポイント
本の中で、いい文章を書くための6つのポイントが紹介されています。
そのポイントとは
- テーマ
- ロジック
- プロット
- スタイル
- ギミック
- エピソード
の6つ。
1つ目の「テーマ」とは、主題のことです。
どんな文章にも、伝えたい核となる内容がなければ相手に伝わりません。
2つ目の「ロジック」とは、文章の理論のこと。
話題があちこちに飛んでしまうと、読者は混乱してしまいます。
3つ目の「プロット」とは、文章構成のこと。
文章の構成がしっかりしていれば、論理的で読みやすくなります。
4つ目の「スタイル」とは、文章のスタイルのこと。
です・ます調やである調など、文章の語句調が統一されていると、読みやすい文章となります。
5つ目の「ギミック」とは、仕掛けのこと。
そして6つ目の「エピソード」とは、具体的なエピソードが文章に盛り込まれていると、読者はイメージしやすいということです。
この6つのポイントを押さえて文章を書けば、自然と人に読まれる文章が完成します。
面白く書けるテーマ選ぶ
文章の上手い人は、自分が面白く書けるテーマを選んで書いています。
自分が興味のないテーマや、体験したことのないテーマだと、なかなか人に読んでもらえる文章は書けません。
だから文章の上手い人は、面白くなさそうなテーマは選ばないんです。
自分の話なんてだれも読みたくない
本書には
読む人は、あなた自身の話など聞きたくもない
と書かれた箇所があります。
見知らぬ人が食べた、ランチの写真と感想を読んでも、面白いと感じる人は少ないはず。
読者は、あなた自身の話なんて聞きたくないんです。
読まれる文章にするには、いい文章を書くための6つのポイント
- テーマ
- ロジック
- プロット
- スタイル
- ギミック
- エピソード
を意識することで、劇的に変化します。
たとえば、「お店でランチを食べたらおいしかった」という文章を、人に読ませる文章に改善してみます。
お店でランチを食べて美味しかったというのは、6つのポイントの中の「エピソード」にあたります。
このエピソードに、ほかの5つのポイントを肉付けしていくことで、読者に役立つ文章が完成します。
たとえば、
- お店の場所
- 客層
- 混雑する時間帯
- おすすめメニュー
といった情報を入れてみてはどうでしょう?
これだけで、そのお店を訪れたことがない人のための、店舗紹介記事になってきます。
あなたがこれから書こうとする文章は、いったい誰のための文章なのか。
これを意識するだけで、書くべき内容が全く違ってきます。
単なるお店やランチメニューの紹介記事ではなく、文章を書く人の独自の視点がそこに入れば、オリジナルで価値ある文章になります。
巻末の「番外トーク」が面白い
巻末には、著者の山口文憲氏と関川夏央氏の対談「番外トーク」が掲載されています。
この対談が、なかなか辛口で面白いんです。
コラムやエッセイの教室は、本質的に意味がない
なんてバッサリ斬り捨てているかと思えば
長い文章は、どんどん削って最終的に50文字くらいにしてしまう。
なんてこともズバズバと書かれています。
うまい文章を書く理論やメゾットなんてあるわけない。あれば私がもうとっくにやっていて、こんな暮らしはしていない。
ただし、下手な文章を書かないコツはある。
かなり辛辣ですが、説得力のある内容ばかり。
読めば新たな気づきが得られるはずです。
『読ませる技術 コラム・エッセイの王道』の気になる点
テクニックは大切、でも良書を読むのも大切
本書では、読まれる文章を書くためのテクニックが掲載されています。
テクニックを身に付けることも大切ですが、たくさんの良書に触れることも大切ではないでしょうか。
毎日少しずつでも本を読むことで、自然と文章力も身についてきます。
ビジネス書もいいのですが、おすすめは小説。
小説では、繊細な感情表現や、情景をリアルにイメージできるようなフレーズが数多く使われています。
そんなフレーズは、普段の生活の中でなかなか触れることができません。
小説を読めば、読者の感情に訴えかける文章とはどのようなものか知ることができます。
さいごに
うまい文章を書く秘訣はありませんが、まずい文章を書かないコツはあります。
そんな文章のコツを、ちょっぴり厳しめに教えてくれるのが「読ませる技術 コラム・エッセイの王道」。
エッセイストの山口文憲さんが講義した、コラム・エッセイに関する講座内容をまとめた本です。
読ませる文章とはいったいどのようなものなのか、本書を読めばその答えが見えてくるはずです。
それじゃ、またね。