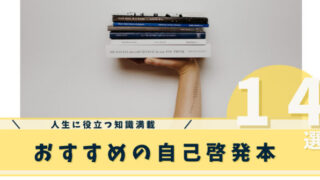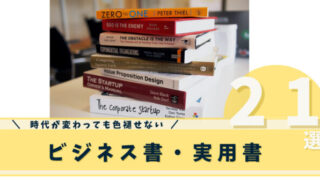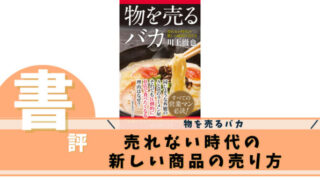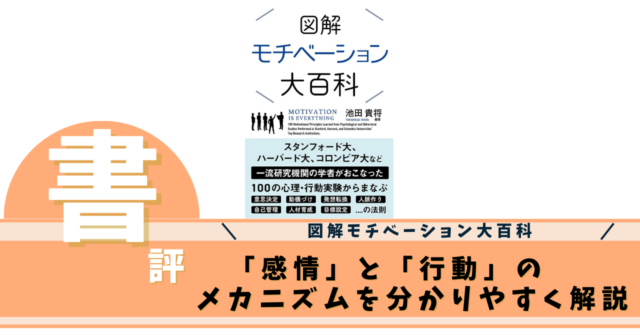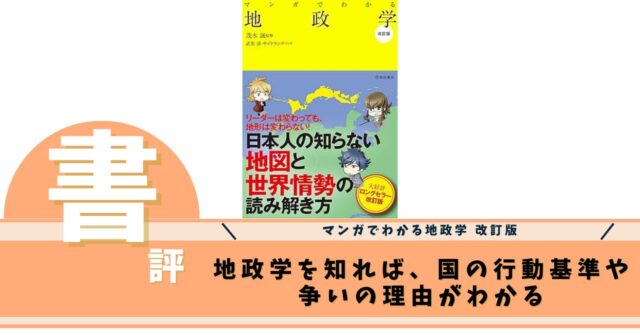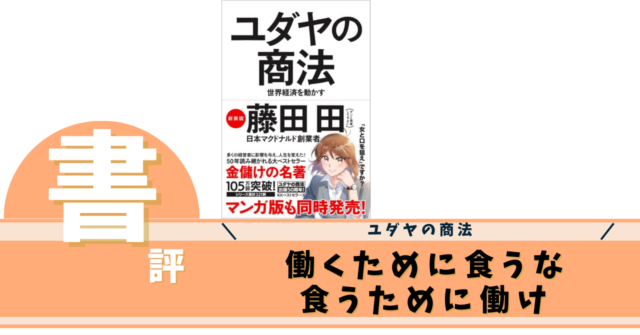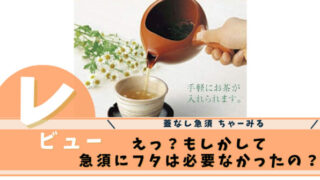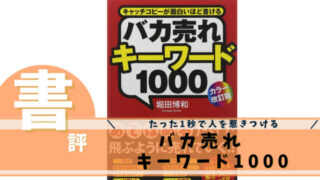こんにちは、いちもくです。
「最近どうも、モチベーションが上がらない」と感じていませんか?
ふとしたきっかけでやってきて、いつの間にか消えてしまうことが多いモチベーション。
でもそれは気まぐれにやってくる存在などではなく、ある法則に従ってわたしたちを動かしているんです。
モチベーションは、仕事だけでなくさまざまな活動への原動力となるもの。
目標を設定するのも、決断を下すのも、人との付き合いも、私たちの生活全てにモチベーションは関わってきます。
そんなモチベーションを科学的に解明したのが、「図解 モチベーション大百科」。
ハーバード大学をはじめ、世界トップクラスの研究機関で研究された行動経済学、実験心理学の結果をもとに、モチベーションの謎を解き明かしています。
今回は、「図解 モチベーション大百科」の重要ポイントを要約していきます。
図解モチベーション大百科の構成
図解モチベーション大百科は
- 動機づけ
- 人材育成
- 目標設定
- 意思決定
- 人脈づくり
- 自己管理
- 発想転換
の7つの章で構成されています。
それぞれの章では、さまざまな理論や法則がまとめられています。
たとえば、動機付けの章では、
- 目標勾配 ゴールを間近に感じさせる
- キャンディ効果 スモールプレゼントをする
- 消費ゴール 報酬を予定する
- 自問式セルフトーク 自分にもお伺いを立てる
- マインドセット 価値観と行動を結びつける
- 内発的動機付け 報酬は1つにする
- 小分け戦略 手数を増減させる
- 同調状態 動きを合わせてから、取り掛かる
- 課題の妥当性 噂に気を付ける
- 証明型と習得型 当人比で評価する
といった形で、モチベーションの動機づけとなる法則が紹介されています。
ゴールまでの距離とモチベーション
本書で紹介されている理論や法則は、わかりやすい具体例とともに紹介されています。
たとえば、「動機づけ 目標勾配」の項目では、相手にゴールを間近に感じさせるための実験内容が紹介されています。
あるコーヒーショップで、スタンプカードを使った実験を行った。
【Aパターン】 コーヒーを10杯飲むと、1杯無料になる
【Bパターン】 コーヒーを12杯飲むと、1杯無料になる。ただしスタンプは最初から2個押してある。
結果、Bパターンのスタンプカードを渡された人達は、Aパターンのスタンプカードを渡された人よりもはるかに多く、無料の1杯を手に入れた。
A・Bパターンのどちらも、残りあと10個のスタンプが必要という事実には違いありません。
でも、スタンプがはじめから2つ押してあると、「もうすでに6分の1も進んでいる」という意識が生まれ、モチベーションが高まるんです。
人は、ゴールに近づけば近づくほどモチベーションが上がるもの。
終わりに手が届きそうな物事については、人は途中で投げ出そうとはしません。
そのためこの実験では、スタンプの数が増していくほど来店頻度が高まる傾向が見られました。
ゴールまでの距離を見るのではなく、現在までどれだけ進んだかという「前進度」に意識を向けることが、ゴールを達成するためには大切だと紹介されています。
「図解モチベーション大百科」の魅力
ビジネスの現場で即応用できる
本書で紹介されている心理・行動実験は、スタンフォード大やハーバード大、コロンビア大など、一流の大学研究機関で行われたものばかり。
そうした心理・行動実験が、100例紹介されています。
全ての実験は、単なる机上の空論ととしてではなく、ビジネスの現場で即応用できるモチベーション理論として紹介されているんです。
見開き2ページで1つのコンテンツ
それぞれの理論や法則は、左右見開き2ページに1つずつまとめられています。
左のページには、実験の概要やその結果が紹介されています。
そして右のページは、実験結果についての詳しい解説が書かれているんです。
各理論や法則を図解入りの見開きで確認できるから、イメージとして頭に残りやすいのが特徴。
辞書がわりに、毎日少しずつ読み進めるのにもおすすめです。
図解 モチベーション大百科の気になる点
研究者の意図とは異なる解説もある
本書の中に「図解モチベーション大百科とは?」という、本の概要について書かれたページがあります。
そこには
編著者による説明は、ビジネスの現場に沿うように解釈された独自のものであり、実際の研究者の意図とは異なる場合があります。
と書かれています。
心理・行動実験の結果を、現代のビジネスシーンに応用しようとした場合、研究を行った研究者の意図とは異なる解説になってしまっているところもあるようです。
さいごに
ふとしたきっかけでやってきて、いつの間にか消えてしまうことが多いモチベーション。
でもそれは気まぐれにやってくる存在などではなく、ある法則に従ってわたしたちを動かしているんです。
モチベーションは、仕事だけでなくさまざまな活動への原動力となるもの。
目標を設定するのも、決断を下すのも、人との付き合いも、私たちの生活全てにモチベーションは関わってきます。
そんなモチベーションを科学的に解明したのが、「図解 モチベーション大百科」。
ハーバード大学をはじめ、世界トップクラスの研究機関で研究された行動経済学、実験心理学の結果をもとに、モチベーションの謎を解き明かしています。
モチベーションを知れば、人生をより豊かに過ごすことができますよ。
それじゃ、またね。