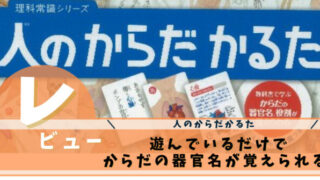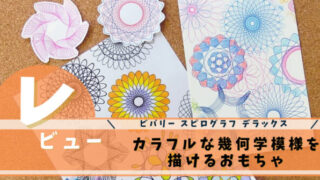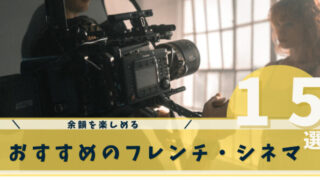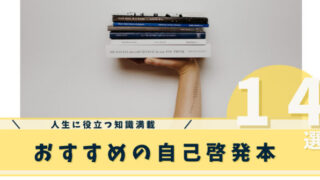こんにちは、いちもくです。
さまざまな知育玩具の中から、子供にどれを与えればいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか?
そんな人におすすめなのが、積み木。
積み木の遊び方は無限大で、積み重ねたり崩したりしながら、創造力や集中力、バランス感覚などを養うことができます。
大人が子供に遊び方を教える必要のあるおもちゃとは違い、子どもが自由に遊べる積み木は、成長と共に遊び方も変化させることが可能。
上質な積み木を選んでおけば、中学生になるまで遊び続けることだってできます。
今回は、そんな積み木の魅力と、おすすめの積み木「カプラ(KAPLA) 魔法の板」を10年使い続けた感想を本音でレビューします。
買い増し続けた積み木
我が家には、中学生の娘が2人います。
娘が幼い頃に初めて購入した積み木は、「木楽舎」の1000ピース積み木でした。
娘が成長するにつれ、1000ピースでは物足りなくなってきたので、定期的に1000ピースずつ積み木を買い増してきました。
買い増した積み木は、カプラ 魔法の板。
積み木を買ってよかったこと
手先が器用になった

積み木を積み上げるためには、繊細な指の力加減が必要です。
幼い頃から積み木に触れていると、物に触れる際の力加減が養われます。
指の力加減だけでなく、力を加える方向によって積み木が崩れる事を繰り返し経験すれば、自然と手先が器用になっていくもの。
僕は料理が大好きなのですが、娘が幼稚園の頃から一緒に料理をするようになりました。
最初はぎこちなかった包丁の使い方も、あっという間にコツをつかんで、上手に肉や野菜をカットしています。
幼い頃から、積み木に親しんでいたことも、包丁のコツを簡単につかめた理由だと思っています。
想像力が養われた

積み木で遊ぶのに、決まりやルールはほとんどありません。
積み上げるだけでも楽しいし、家や街をつくることもできます。
娘は、積み木で絵を描くのが大好きでした。
これは娘が幼い頃、僕を積み木で描いてくれたもの。

「今度のクリスマスプレゼントに、サンタさんに自転車をお願いしたいな」
と言いながら、積み木で自転車をつくってみたり。

叱られた際に避難するための、シェルターをつくってみたり。

シェルターを自分の背の高さまで積み上げたのですが、中に入れないことに気づいて落ち込んでいました。
ほかにも、自宅のマンションから打ち上げ花火を見た夜に、積み木で花火をつくってたこともありました。

ひな人形を飾ってたら、参道付きのひな人形を積み木でつくったこともありました。

遊び方のコツが分かれば、自由な発想でいろんなものをつくれるのが、積み木の魅力です。
算数の図形問題が得意になった

小学校の算数では、立方体の面積を求めたり、隠れている立方体の数を求める問題が出てきます。
積み木に長年親しんでいた娘は、図形問題が得意ジャンルになった様子。
ずっと100点を取り続けています。
積み木は、空間認識能力や立体の概念を理解する力を高めてくれるおもちゃなのかもしれません。
積み木遊びのポイント
とにかく褒める

子どもが積み木で何かをつくったら、誰かに見せたいと思う場合がほとんど。
自由な発想で積み上げられた積み木を見て、一緒に喜んだり褒めたりすれば、子どもは達成感や満足感を得られるはずです。
嬉しくなれば、もっと新しいものをつくってみようと、想像力を更に働かせて夢中になるのではないでしょうか。
お手本は大切

積み木で遊んだことのない子どもの前に、たくさんの積み木を目の前に置いたとしても、遊び方が分からないかもしれません。
また、積み木を積み上げようとしても、上手に積み上げられないことだってあるはず。
だから我が家の場合は、ボーリング遊びから始めました。
大人が積み上げた積み木を、ボールを転がしてくずす遊びです。
娘は
「積み上げられた積み木をくずすのは面白い。面白いから、今度は自分で積み上げてみよう」
と考えたみたいで、すぐに自分で積み木を積み上げて遊ぶようになりました。
写真に残してみる

子どもが積み木でつくったものは、僕はできるだけ写真に残すようにしています。
数年後、子どもにその写真を見せると
「どうやってこんな凄いものをつくったんだろう?」
なんて不思議そうな顔をする事もあるんです。
思い出にもなるし、子どもの想像力を更に刺激することにも繋がっていそうです。
積み木選びのポイント
積み木の通販サイトを見ると「年齢に合った積み木を選びましょう」と書かれていることが多いようです。
でも僕は、年齢に合わせて積み木を買い直す必要はないと感じています。
積み木を選ぶ際に参考にした本がこちら。
積み木だけでなく、子どもに与えるおもちゃ選びのヒントが満載の本です。
本を参考に、次の5つのポイントに注意しながら積み木を選びました。
積み木選びのポイント① 白木素材の積み木
積み木の素材は、断然「木」がおすすめ。
木は生き物です。
生きていた木のぬくもりを感じられる、白木素材の積み木は見た目も良く、手触りも抜群です。
使い続けることで、段々と手に馴染んできます。
積み木が傷ついたり、手垢でよごれてきたとしても、それも愛着や思い出だと思えば気にならないもの。
程良い重さと安定感があるので、高く積み上げるのにもおすすめです。
積み木選びのポイント② 角が丸くなっていない積み木
安全性を考えて、角を丸く処理した積み木もあります。
でも、そんな積み木は積み上げた時の安定感や美しさがありません。
しっかりと角のある積み木は、積み上げた時にピッタリはまって、見た目が綺麗。
「角が尖っていると危険」
と考える人もいるかもしれませんが、家の中にはもっと危険なものがたくさんあるはずです。
積み木で遊んでいるうちに、子どもは「角が尖っているものは痛いけれど、平らな部分は痛くない」という当たり前のことを学べます。
積み木選びのポイント③ 色が塗られていない積み木
僕が買い続けてきた積み木は、白木そのままの色の積み木です。
色があった方が、子どもの色彩感覚を育むのに適しているという意見もありますが、僕は積み木に色を求めるのはナンセンスだと思っています。
そもそも、子どもの生活する世界には、たくさんの自然の色が溢れています。
また、積み木に色が塗られていることで、遊びが制限されてしまう可能性だってあるはず。
たとえば、黄色い積み木を使って何かをつくろうとしても、足りなくなったら別な色の積み木を使う必要が出てきます。
色が塗られていない白木の積み木であれば、色が足りなくなるというストレスはありません。
色は、遊んでいる子供が自由にイメージすればいいのではないでしょうか。
色が塗られていなくても、白木の微妙な色の違いはあります。
こうした繊細な違いを理解する感覚は、色が塗られた積み木で遊んでいては育まれない気がします。
積み木選びのポイント④ 四角い積み木
我が家で購入した積木は、
- 正方形
- 長方形
- 台形
の形をした積み木だけです。
三角形の積み木も販売されていますが、三角形の積み木の上には積み木を積めません。
だから三角形の積み木は、家や建物の屋根にしか使えないパーツなんです。
三角形の積み木を置いてしまうと、それ以上積み木を積み上げられないので、遊びはそこで一旦ストップしてしまいます。
積み木の魅力は、無限に積み上げられるところではないでしょうか。
だから我が家では、正方形・長方形・台形の積み木のセットを購入しました。
積み木選びのポイント⑤ 数が多い積み木
10ピースや20ピース程度の積み木セットだと、すぐに積み木が足りなくなって、遊びがそこで終わってしまいます。
だから僕は、1000ピース入っている積み木セットを何度か購入してきました。
1000ピースあれば、2~3人で遊ぶのに十分な量です。
でも、積み木で街や巨大な塔をつくろうと思ったら、1000ピースでは全く足りません。
3000ピースほど用意できれば、積み木の残りを気にせずどんどん新しいものをつくって遊べます。
娘は何度か、自宅の和室の天井に届くような巨大な積み木の塔と、塔の周りに広がる街を1人でつくったことがありました。

3000ピースくらいあれば、大きな作品をつくる楽しさを存分に味わえます。
僕が買い増し続けた積み木
僕が求める積み木の条件は
- 白木素材
- 角が丸くなっていない
- 色が塗られていない
- 三角や丸ではなく、四角い形をしている
- とにかく数が多い
この条件を満たす積み木、『KAPLA(カプラ)の魔法の板』を、定期的に買い増し続けてきました。
積み木は最高ですよ。
大人も日頃のストレスを忘れて、夢中になって遊べるおもちゃです。
それじゃ、またね。