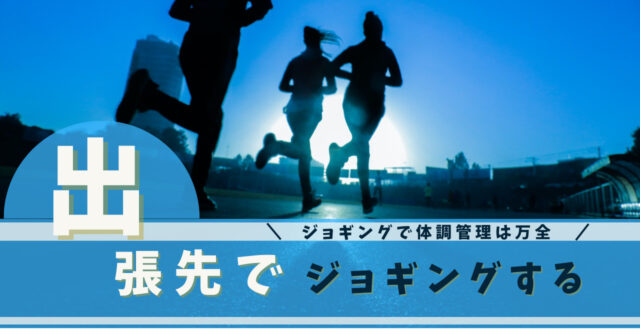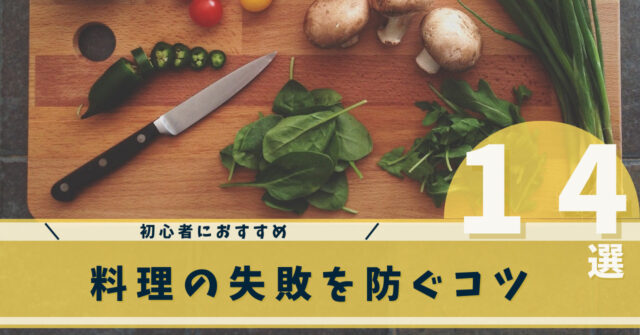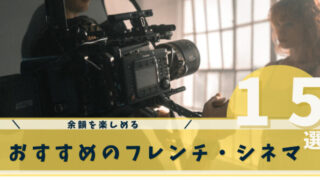こんにちは、いちもくです。
そういえばマヨネーズやケチャップが残り少なくなっていたけれど、うっかり買い忘れていた、なんて経験はありませんか?
そんな人におすすめなのが、家族で共有できる生活必需品管理表を自作してみること。
我が家は4人家族なのですが、生活必需品の中で残り少なくなってきたアイテムがあれば、気が付いた人が買ってこれるよう一覧表を活用しています。
生活必需品管理表を使い始めてからは、小学生の娘も一人で買い物に行くのが楽しくなった様子。
今回は、家族で活用できる生活必需品管理表について詳しく解説します。
Twitterで話題になった「生活必需品管理表」
生活必需品管理表は、一時期Twitterでも話題になったアイデアです。
用意するものは、ホワイトボードと磁石。
「砂糖」「塩」「醤油」といった、生活必需品の名前を磁石の両面に書いておき、残り少なくなったら裏返しておくというシンプルな活用方法です。
実際につくってみた
「生活必需品管理表」をつくるために、まず用意したものは、ホワイトボード。
裏面に磁石がついているホワイトボードがおすすめです。

もう1つ必要なのが、裏表で色が違うマグネットシート。
そしてラベルプリンター。
工程① 生活必需品の品目を2枚ずつ準備

ラベルプリンターを使って、生活必需品の品目を2枚ずつ印刷します。
それを磁石の両面に貼っていきます。
工程② 磁石をカットしてシールを貼る

ラベルのシールサイズに合わせて、磁石をカット。
カットしたら、裏表両面にシールを貼ります。

運用開始

あとは裏面に磁石のついたホワイトボードを、冷蔵庫に貼るだけで完成です。
使ってみて感じた「生活必需品管理表」のメリット
家族全員が今必要なものを知れる
家族全員がスマホを持っていれば、スマホアプリで買い物リストを共有することもできるかもしれません。
でも「生活必需品管理表」を使えば、メモを増やしたり消したりする必要がなく、磁石を裏返すだけで必要なものが何なのか分かります。
追加や削除が自由にできる
我が家で最初につくった生活必需品の品目は、26種類。
しばらく運用を続けていると、ホワイトボードに追加しておきたい品目や、必要ない品目が分かってきます。
家庭に合わせて、簡単に品目を追加したり削除することができるのは便利です。
生活必需品以外にも応用可能
娘は学校に行く際、よく忘れ物をしていました。
だから「ランドセルの中身管理表」もつくってみたんです。
授業で何が必要なのかを「見える化」することで、忘れ物をすることが劇的に減りました。
ほかにも、「旅行グッズ管理表」なんてのもおすすめです。
使ってみて感じた「生活必需品管理表」の気になる点
たまに買い物が被ってしまう
「生活必需品管理表」で裏返しになっている品目を、写真に撮ったりメモして出かけることが増えました。
でも、時々買った商品が被ることがあるんです。
家族全員が「生活必需品管理表」をチェックしているわけなので、買い物が被ってしまうのも仕方ないかもしれません。
日持ちする消耗品のみを生活必需品管理表に掲載しておけば、買い物が被ってもストックしておけるので安心です。
さいごに
生活必需品管理表を使い始めてからは、娘が積極的に家事を手伝うようになりました。
娘は、ゲーム感覚で管理表を裏返しているようです。
夏休み期間中など、お手伝いをお願いしたいタイミングで導入してみるのもおすすめです。
ライフスタイルや目的に合わせて、いくらでも応用できる便利な管理表ですよ。
それじゃ、またね。

https://ichimokusan.info/greenclickledreview/