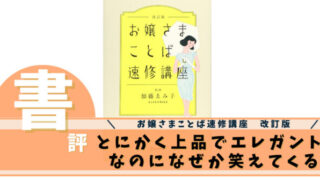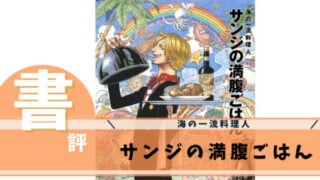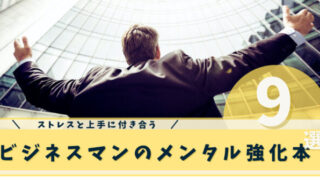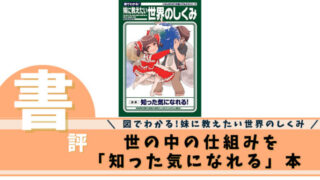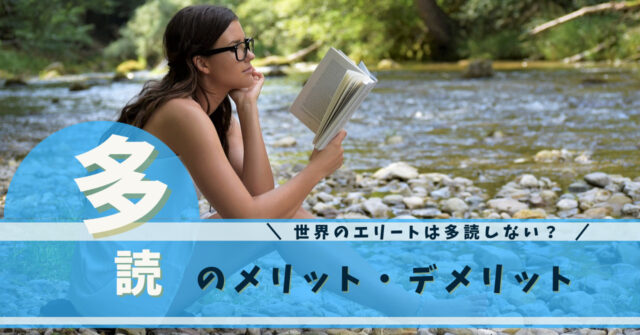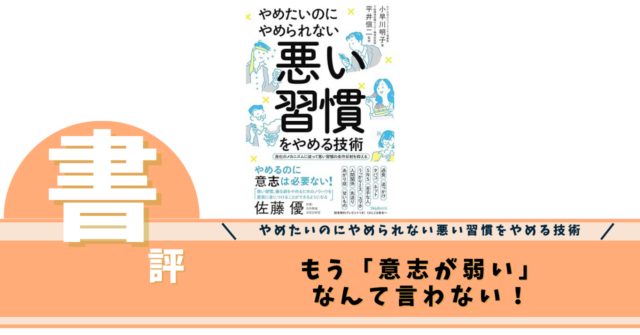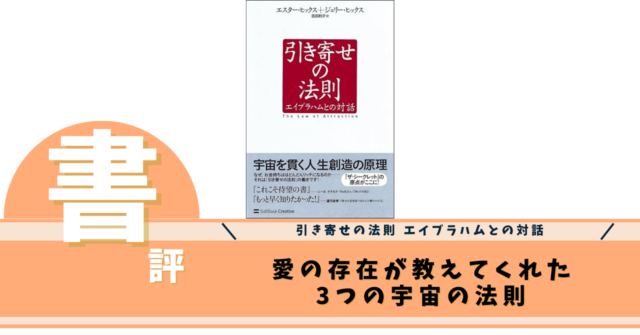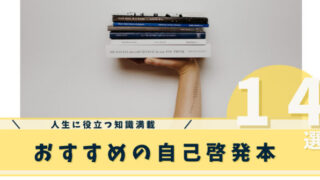こんにちは、いちもくです。
東洋経済ONLINEで、こんな記事を見つけました。
記事を読んで、「そういう考え方もあるのかなぁ」とは思いましたが、僕は完全に多読派。
本を多読するデメリットもあるとは思いますが、メリットの方が断然多いと実感しています。
東洋経済の記事の概要
東洋経済の記事に書かれていた内容を簡潔にまとめると
- LINEの社外取締役やスタンフォードの客員研究員を務める鳩山玲人氏が、日本とアメリカの大学生の読書に対するとらえ方の違いをまとめた記事。
- アメリカのビジネススクールに通う学生は、ほとんど本を読まない。彼らは本を読むことを目的とせず、本をどう使うかという実践に重きを置いている。
- アメリカのビジネススクールに通う学生は、理論や方法論が書かれた本を読むことはあまりない。
- 手元に置く本を10冊に絞ってみると良い。10冊の中から、今日読む本を決めることで、本を「ToDoリスト」のように本を使うことができる。
といった内容でした。
記事の執筆者である鳩山玲人さんは、『世界のエリートは10冊しか本を読まない』という本を執筆しているようです。

僕が多読を続ける理由
僕は毎月、50冊以上本を読んでいます。
読む本のジャンルは、小説、ビジネス書、絵本、料理のレシピ本、歴史解説本、実用書、漫画などさまざま。
僕が本を読む理由は、仕事や勉強のためだけではありません。
いろんな著者と、本を通じてコミュニケーションを取るためです。
僕は普段営業の仕事をしているのですが、お酒の席で相手の趣味嗜好や考え方、過去の経験を聴くのが大好きなんです。
本も同様で、普段の生活ではなかなか知ることができない、いろんな人の考えに触れられるツールだと思っています。
だから僕が本を読む理由は、いろんな人の深い考えやその人の人生を知るのが面白いから。
僕にとって本は、『世界のエリートは10冊しか本を読まない』で紹介されている「ToDoリスト」のように活用するためのツールではありません。
筆者の考え方や生き様に触れるための、血の通ったコミュニケーションツールなんです。
多読のメリット
普段知り合えない人の考え方に触れられる
本を多読する1番のメリットは、成功者の考え方や体験談を、本を通じて知ることができるということ。
著名人と直接会って話をしようと思っても、簡単には出来ません。
でも本であれば、わずか1500円ほどで気になる人の考え方に触れられます。
しかも、自分の好きなタイミングで。
さまざまな著者と、本を通じて「対話」することで、それまで自分になかった視点や考え方を学ぶことができます。
本は、まさに人類にとって偉大な発明であり、叡智の結晶なのではないでしょうか。
自分にとって価値ある本を選べるようになる
本を多読し続けていると、徐々に読む本のジャンルが偏りがちになります。
読む本が偏ってきたなと感じたら、新しいジャンルの本に挑戦してみるのがおすすめです。
本を多読するようになると、今の自分に必要な本を見分ける力が鍛えられてきます。
本のジャンルが偏っているのは、もしかすると今の自分に必要な情報を無意識に求めているからなのかもしれません。
ちなみに僕の場合、ビジネス書を読む機会がだんだんと減ってきました。
有益な情報が書かれたビジネス書もたくさんありますが、内容が薄い本も多いのが事実。
300ページくらいのビジネス書を読み終わって「これって、10ページで済む内容を間延びさせただけなんじゃないの?」なんて思える本もたくさんあります。
そんな本は、数年後には絶版になってしまっていることも多いんです。
だから最近は、ビジネス書は購入するのではなく、オーディオブックを使って試聴しています。

オーディオブックであれば、通勤・通学やジョギング中などに、ながら読書ができてとっても便利。
多読していると、自分にとって本当に価値ある本が段々と段々と分かってくるので、効率良く読書する方法も身についてきます。
読書スピードが上がる
日本では毎年、10万冊近い新刊本が発行されています。
全てを読むことはできないので、現在発売されている本の中から自分に必要な本を選択する必要があります。
僕の場合は、通勤時間に読書したり、隙間時間を使って読書しています。
隙間時間を効率的に使えば、1日に1~2冊の本を読むことも可能。
最近は、1日に3冊の本が読めるようになってきました。
わざわざ速読法を学ばなくても、多読を続けることで、自然と本を読むスピードが上がっていきます。
多読のデメリット
「速読」「熟読」「精読」の使い分けが必要
読書に慣れていない人は、とにかくたくさんの本を読もうとして、斜め読みや読み飛ばししてしまう人がいます。
本の魅力は、普段なかなか触れることができない、美しい言葉を使った表現にもあります。
本を読み終わった後に、1人でじっくり考える時間を取ることが、読書に欠かせない大切なことです。
つまり、本の余韻を楽しむということ。
むやみやたらと多読するのがいいわけではありません。
自分にとって有益な情報や、感動できる内容が書かれた良書に出会ったら、しばらく新しい本を手に取るのはやめて、本の内容をじっくり咀嚼する時間をつくるのがおすすめです。
「本の知識は絶対」という勘違いに陥りがち
多読する人が陥りがちなのが、本から得た知識が絶対に正しいと信じ込んでしまうこと。
たとえば、病院に行って医者から病気の説明を受けても
「本にはこう書かれていましたけど?」
なんて、医者の話を聴こうとしない人もいます。
法律や家事についても同じで、本に書かれていることを盲信するあまり、リアルな人間関係で話を聞き入れなくなってしまう人もいます。
「知識をひけらかすだけの面倒臭い人」
と思われてしまうと、人間関係がうまく行かなくなる可能性があるので注意が必要です。
多読は、本を通じて著者とコミュニケーションを取るきっかけになれば十分。
偏ったジャンルの本を読み続けたり、知識を増やすことを目的に多読を続けていると、視野が狭くなってしまう可能性があります。
本は、普段会って話をすることができない、著者とのコミュニケーションツールとして利用するのがおすすめです。
孔子や老子といった偉大な思想家とも、本を使えば時空を超えてその考え方に触れることができます。
さいごに
『世界のエリートが本の「多読」をしないワケ』という本の紹介記事を読んで、多読について考えたことをまとめてみました。
アメリカのトップビジネススクールに通う学生は、毎日の授業や膨大な数のレポート作成に忙しいので、授業に関係のない読書はできないのかもしれません。
僕は本を「筆者とのコミュニケーションツール」だと考えています。
本との付き合い方に、正解はないのかもしれませんね。
それじゃ、またね。