こんにちは、いちもくです。
中学受験を目指す子を持つ親は、子供を塾に通わせるか、家庭教師に来てもらうか、はたまたオンライン学習を利用してみようかと迷っていませんか?
どの勉強方法を選ぶかによって、子供の人生が大きく変わってしまうかもしれません。
なぜならば、子供の性格やレベルに合った勉強方法を選ばないと、結果は出せないから。
どれだけ塾へ通わせたり、家庭教師に勉強を教えてもらったとしても、子供に合ったやり方でなければ成績は伸びません。
では、どうすれば自分に合った勉強方法を見つけられるのか。
最初にやっておきたいのは、それぞれの教育サービスの特徴を知り、比較することです。
我が家には中学生の娘が2人いますが、2人とも第一志望のカトリック系難関私立中学に無事合格して、今は楽しく学校生活を送っています。
中学受験に備えてさまざまな準備をしましたが、一番重要だったと思えるのは、娘の性格や学習レベルに合った勉強方法を比較検討すること。
今回は、中学受験を控えた親向けに、塾・家庭教師・オンライン学習それぞれの特徴と魅力について解説していきます。
「塾」「家庭教師」「オンライン学習」の違い
費用の違いを比較

親であれば気になるのは、「塾」「家庭教師」「オンライン学習」のどれが子供の学力を一番向上させられるかということ。
もちろん、それぞれの費用も気になるところです。
それぞれを、週に2回受講した場合の相場を比較してみました。
| 集団塾 | 約20,000円/月 |
| 個別塾 | 約30,000円/月 |
| 家庭教師 | 約35,000円/月 |
| オンライン学習 | 約10,000円/月 |
地域によって、月々の料金相場は異なります。
また、月々の授業料以外にも、入会金や教材費などの費用が必要な場合があります。
たとえ月々の授業料が安かったとしても、学力の向上が見込めなければ利用する意味はないでしょう。
通学時間で比較

塾・家庭教師・オンライン学習を利用するのは、基本的に学校から帰宅した後。
学校から帰ったらすぐに、次の学習のための準備をしなければいけません。
自宅からどれだけ離れているかは、学習時間を確保する上で重要なポイントです。
| 集団塾 | 教室までの通学が必要 |
| 個別塾 | 教室までの通学が必要 |
| 家庭教師 | 通学の必要なし |
| オンライン学習 | 通学の必要なし |
塾に通う場合は、自宅からの距離を考慮しておく必要があります。
体験レッスンで比較

どの勉強方法を選ぶにしても、大切なのは子供との相性。
子供にとって、先生と一緒に長時間過ごさなければならないのは、親が考える以上にストレスが大きいはずです。
だから体験レッスンを通じて、子供と先生の相性を見極めることは大切。
楽しく勉強できることが理想かもしれませんが、ときには厳しく、的確に指導できる先生であれば理想的です。
| 集団塾 | 体験レッスンのある教室が多い |
| 個別塾 | 体験レッスンのある教室が多い |
| 家庭教師 | 体験レッスンのある派遣先が多い |
| オンライン学習 | 体験レッスンがある場合が多い |
いずれの勉強方法にも、体験レッスンが用意されている場合がほとんど。
体験レッスンを通じて、授業内容だけでなく、先生との相性を見極められるかが大切です。
メリットとデメリットを考えてみた
集団塾を選ぶメリット
集団塾では、1~2人の講師が10人以上の生徒に対して授業を行います。
小学校の授業スタイルと似ているので、子供にとってはストレスが少ないかもしれません。
集団塾に通うメリットは、何よりも中学受験対策のノウハウが充実しているところ。
教科別の、専門講師がいる塾がほとんどです。
また、教室で一緒に授業を受けているのは、中学受験を目的とした児童ばかり。
毎日良い刺激を受けられるのはメリットかもしれません。
個別指導塾や家庭教師よりも、コストは比較的安めです。
集団塾を選ぶデメリット
集団塾に通う上で気を付けたいのが、授業についていけなくなった場合のフォロー方法です。
講師は一人でたくさんの生徒を把握しなければならないので、生徒一人一人の苦手分野を克服するまでフォローできないことがあります。
また、授業のスタイルは基本的に塾が決めたスケジュールに合わせて行われます。
子どもの苦手分野克服が目的であれば、集団塾の授業スタイルには合わないこともありそうです。
個別塾を選ぶメリット
個別指導塾とは、講師1人が生徒1~3人程度を指導する形式の塾。
最近は、個別指導塾が全国で増えています。
集団塾に比べて指導がきめ細やかで、家庭教師よりも月謝が安いところが魅力。
たいていの個別塾には、自習室が設けられています。
授業がない日でも、自習室が解放されている塾が多いので、宿題や課題をこなすために利用することができます。
個別指導塾を選ぶデメリット
講師とマンツーマンで学習できる個別指導塾ですが、塾まで通う必要があります。
自宅からの距離を考慮して、教室を選ぶ必要があるでしょう。
ほかにも、塾によっては家庭教師と同程度か、それ以上の月謝が必要なところがあります。
体験入学を通して、子供と先生の相性や、月謝については必ず確認しておく必要があるでしょう。
家庭教師を選ぶメリット
家庭教師のメリットは、マンツーマンでじっくり指導してもらえるところ。
子どもの得意分野と苦手分野をしっかり把握した上で、最適なカリキュラムを組んでもらえます。
分からない箇所を徹底的に指導してもらえるところは、家庭教師の一番の魅力と言えるでしょう。
家庭教師を選ぶデメリット
家庭教師を選ぶ上で、一番気になるのが授業料。
塾に比べると、授業料は高額な場合がほとんどです。
ほかにも、子供との相性も気になるところ。
マンツーマンの指導なので、教師のスキル次第で成績の伸びは違ってきそうです。
オンライン学習を選ぶメリット
オンライン学習とは、ZOOMで授業を受けたり、毎月届く教材を使って学習するスタイルです。
タブレットやパソコンを使って学習できるので、好きな時間に勉強を進められるのがメリット。
自宅で学習に取り組めるので、近くに塾がない地域でも受験勉強を進められます。
オンライン学習を選ぶデメリット
オンライン学習は、継続するのが意外と難しいんです。
好きな時間に学習できるということは、いつまで経っても勉強を始めない可能性もあるということ。
分からない箇所が出てきても、すぐに質問できない可能性もあります。
親が定期的に学習の進捗状況をチェックする必要のある学習スタイルです。
おすすめの個別塾
中学受験家庭教師ドクター
中学受験専門の個別指導塾と、家庭教師派遣を行っている中学受験家庭教師ドクター。
一般的な塾や家庭教師センターとは違い、中学受験専門のプロ講師が運営しています。
だから中学受験対策に絞った学習が可能。
子どもの理解度や学力に合わせて、最適なカリキュラムを組んでもらえます。
\失敗しない中学受験とは?/
おすすめの家庭教師
家庭教師のノーバス
関東を中心に、大学生やプロの家庭教師を紹介する家庭教師のノーバス。
目標、指導内容、先生の個性など、全部で12の項目を選択することで、子どもにぴったりの教師や専用カリキュラム、指導方法をオーダーメイドできます。
シンプルな料金体系が魅力。
公式サイトに表示されている料金以外は一切必要ありません。
\無料体験授業受付中/
おすすめのオンライン学習
オンライン家庭教師 スナップアスク
勉強で分からないところがあったら、いつでもどこでも優秀なチューターと呼ばれる人たちに質問できるアプリ。
イメージとしては、
「・・・この問題どうやって解けばいいのか分からない。写真に撮ってアップするから、解き方教えて!」
と、LINEで先輩や先生に質問するような感覚です。
分からないことがあったら、いつでもどこでも質問可能。
質問に回答してくれるのは、難関大学出身者や塾講師など。
チャットで回答してくれるだけでなく、必要であれば動画で解説を送ってもらえます。

インターネット家庭教師Netty(ネッティー)
難関大学出身者や、現役で大学に通う人気教師の授業を、インターネットを通じて受講できる家庭教師サービス。
パソコンとインターネット環境があれば、自宅で受講できます。
映像と音声を使って、リアルタイムに対話しながらの授業。
分からない箇所があれば、すぐに質問できます。
塾に通うより費用を抑えられるのも魅力です。
\入会金・教材費無料/
e点ネット塾(公立中高一貫受検対策)
公立の中高一貫校受検に絞って、講義とテキストが用意されているオンライン塾。
全国の公立中高一貫校で出題された適性検査の問題が、各教科別に揃っています。
自宅にいながら、公立中高一貫校の受検対策ができるサービスです。
\受験問題に特化した対策授業/
さいごに
中学受験を目指す子を持つ親は、子供を塾に通わせるか、家庭教師に来てもらうか、はたまたオンライン学習を利用してみようかと迷っていませんか?
どの勉強方法を選ぶかによって、子供の人生が大きく変わってしまうかもしれません。
なぜならば、子供の性格やレベルに合った勉強方法を選ばないと、結果は出せないから。
どれだけ塾へ通わせたり、家庭教師に勉強を教えてもらったとしても、子供に合ったやり方でなければ成績は伸びません。
では、どうすれば自分に合った勉強方法を見つけられるのか。
最初にやっておきたいのは、それぞれの教育サービスの特徴を知り、比較することです。
我が家には中学生の娘が2人いますが、2人とも第一志望のカトリック系難関私立中学に無事合格して、今は楽しく学校生活を送っています。
中学受験に備えてさまざまな準備をしましたが、一番重要だったと思えるのは、娘の性格や学習レベルに合った勉強方法を比較検討すること。
子どもの学力や理解度に合わせて、学習環境を整えていくことが大切ですよ。
それじゃ、またね。

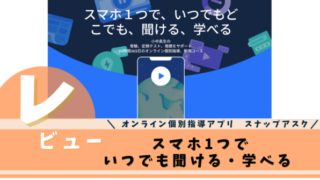




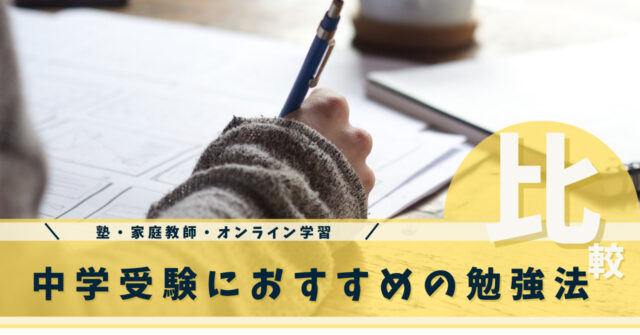





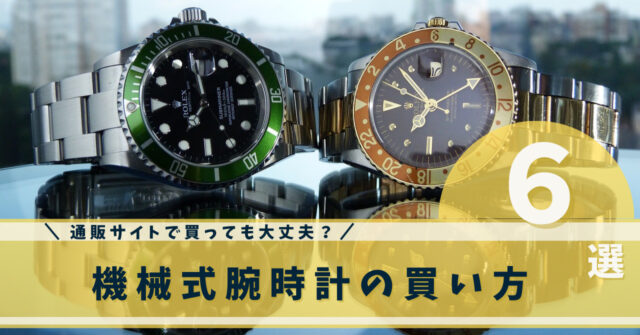
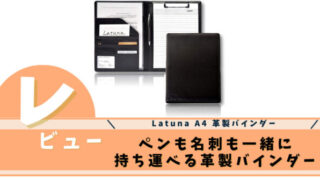


コメントを投稿するにはログインしてください。